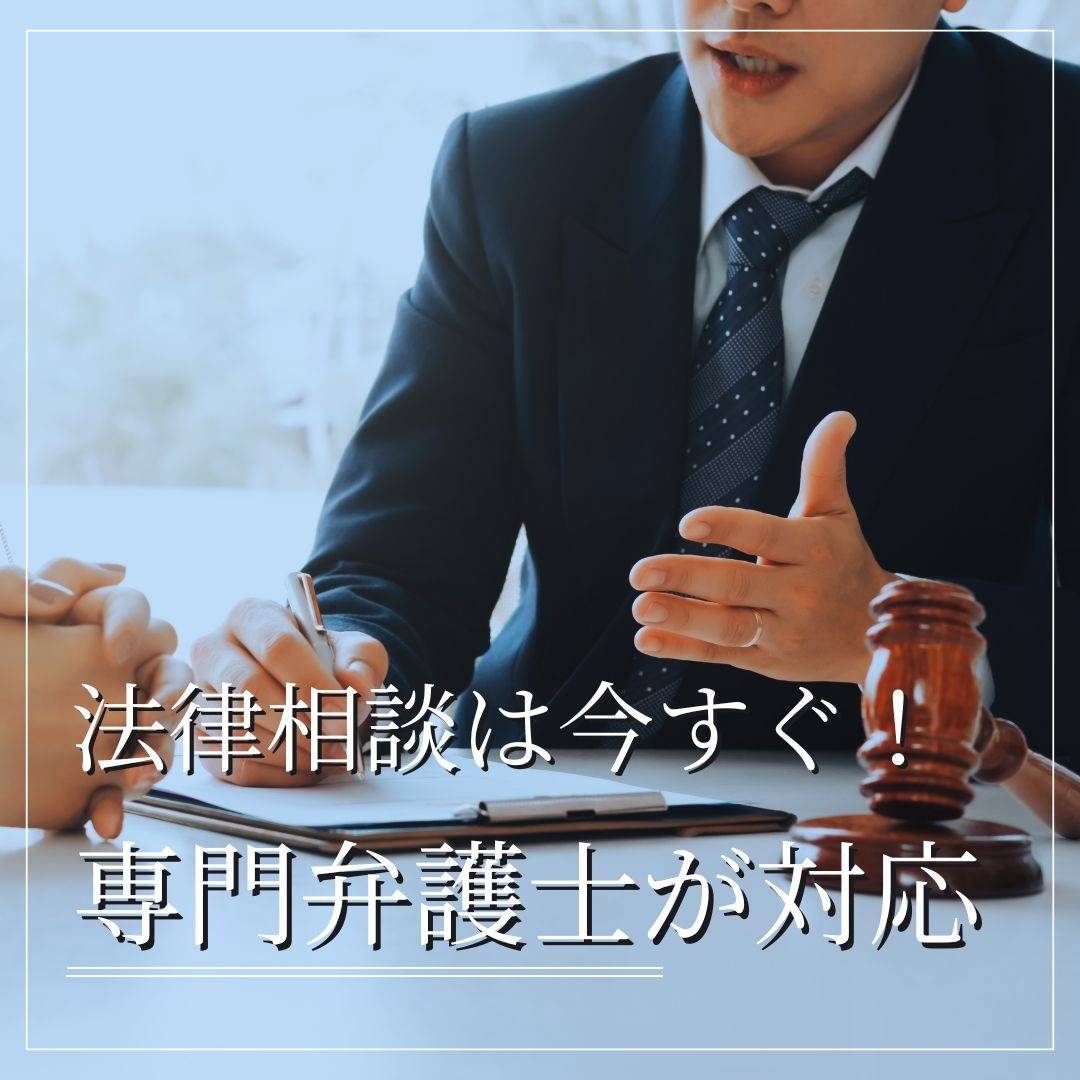【AI補助記事】職場のパワーハラスメント防止対策について - 厚生労働省指針の要点解説
2025/07/31
職場のパワーハラスメント防止対策について - 厚生労働省指針の要点解説
はじめに
令和4年4月1日から、企業規模に関わらず、職場におけるパワーハラスメント防止対策を講じることが事業主の義務となりました。この義務化は労働施策総合推進法の改正に基づくもので、すべての事業主が職場におけるパワーハラスメント防止措置を講じなければならないことを意味します。本記事では、厚生労働省が定めた指針の要点を解説し、企業が取るべき具体的な対策について詳しく説明いたします。
パワーハラスメントの定義
厚生労働省の指針では、職場のパワーハラスメントを以下のように定義しています。
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
この定義において重要なのは、3つの要素がすべて満たされる必要があることです。また、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
①優越的な関係を背景とした言動
優越的な関係とは、上司と部下の関係だけでなく、同僚や部下であっても、業務上必要な知識や豊富な経験を有している場合、集団による行為で抵抗・拒絶が困難な場合なども含まれます。一般的には上司は部下より強い立場にありますが、新しく配属された上司に対して部下が過大な要求をしたり、ITに詳しくない上司に対して部下が暴言を吐いたりすることも、パワーハラスメントとなります。
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とは、業務の目的を大きく逸脱した行為や、業務を遂行するための手段として不適当な行為を指します。
③労働者の就業環境が害される
労働者が身体的・精神的苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の就業上看過できない程度の支障が生じることを指します。
職場の定義
事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。勤務時間外の「懇親の場」、社員寮や通勤中などであっても、実質上職務の延長と考えられるものは職場に該当する場合もあります。
パワーハラスメントの代表的な6つの類型
厚生労働省の指針では、パワーハラスメントを以下の6つの類型に分類しています。
-
身体的な攻撃
- 殴る、蹴る、物を投げつける等の暴行・傷害
-
精神的な攻撃
- 人格を否定するような暴言、他の労働者の前での威圧的な叱責、必要以上に長時間の厳しい叱責
-
人間関係からの切り離し
- 仲間外し、無視、隔離・仲間外し、別室への隔離
-
過大な要求
- 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
-
過小な要求
- 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
-
個の侵害
- 私的なことに過度に立ち入ること
ただし、社内のパワーハラスメントの有無を判断する際は、類型にこだわり過ぎず、柔軟な視点で判断することが大切です。
事業主が講ずべき措置
厚生労働省の指針では、事業主が講ずべき措置として以下の内容を定めています。
1. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- パワーハラスメントの内容、方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
- パワーハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
2. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
- 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
3. 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
- パワーハラスメントが確認できた場合、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと
- 再発防止に向けた措置を講ずること
4. 相談者・行為者等のプライバシー保護のために必要な措置
- 相談者や行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
5. 相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止
- 労働者が相談を行ったこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
パワーハラスメント対策の重要性
厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」によれば、労働者の5人に1人が「過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがある」と答えています。この現状を踏まえると、パワーハラスメント対策は企業にとって待ったなしの課題と言えるでしょう。
パワーハラスメントが発生することにより、企業には以下のような悪影響が生じる可能性があります:
- 従業員の精神的・身体的健康への影響
- 生産性の低下
- 離職率の増加
- 企業の信頼失墜
- 法的リスクの増大
- 採用活動への悪影響
パワーハラスメントが明るみに出た企業では採用活動に支障が出ることもあります。少子高齢化が進む昨今においては、採用活動は長期の経営戦略の重要課題であり、無視できない悪影響が生じる可能性があります。
企業が取るべき具体的な対策
1. 就業規則等の整備
パワーハラスメント防止に関する方針や対処方法を就業規則に明記し、全従業員に周知することが重要です。
2. 研修・教育の実施
管理職を含む全従業員を対象として、パワーハラスメントに関する研修を定期的に実施し、意識向上を図る必要があります。
3. 相談窓口の設置
内部・外部を問わず、相談しやすい環境を整備し、相談窓口の存在を周知することが求められます。
4. 迅速かつ適切な対応体制の構築
問題が発生した場合に、迅速かつ公正な調査・対応ができる体制を整備することが不可欠です。
5. 再発防止策の実施
問題が発生した場合は、原因を分析し、再発防止に向けた具体的な改善策を講じることが重要です。
まとめ
職場におけるパワーハラスメント防止対策は、すべての事業主に課せられた法的義務です。厚生労働省の指針に基づき、適切な防止措置を講じることは、従業員の働きやすい環境を確保し、企業の持続的な発展につながります。
企業は、パワーハラスメントの定義や類型を正しく理解し、予防から事後対応まで包括的な対策を講じることが求められます。また、一度対策を講じれば終わりではなく、継続的な見直しと改善を行い、より良い職場環境の実現に向けて取り組むことが重要です。
パワーハラスメント対策に関してご不明な点がございましたら、労働問題に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
本記事は厚生労働省の指針等を基に作成しており、法的助言を目的としたものではありません。具体的な事案については、専門家にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
オンライン法律事務所タマ
東京都東大和市上北台3-429-24 サンライズビル305
電話番号 : 080-7026-2558
弁護士として労働問題に対応
弁護士による企業法務の相談
弁護士との顧問契約で築く信頼
----------------------------------------------------------------------